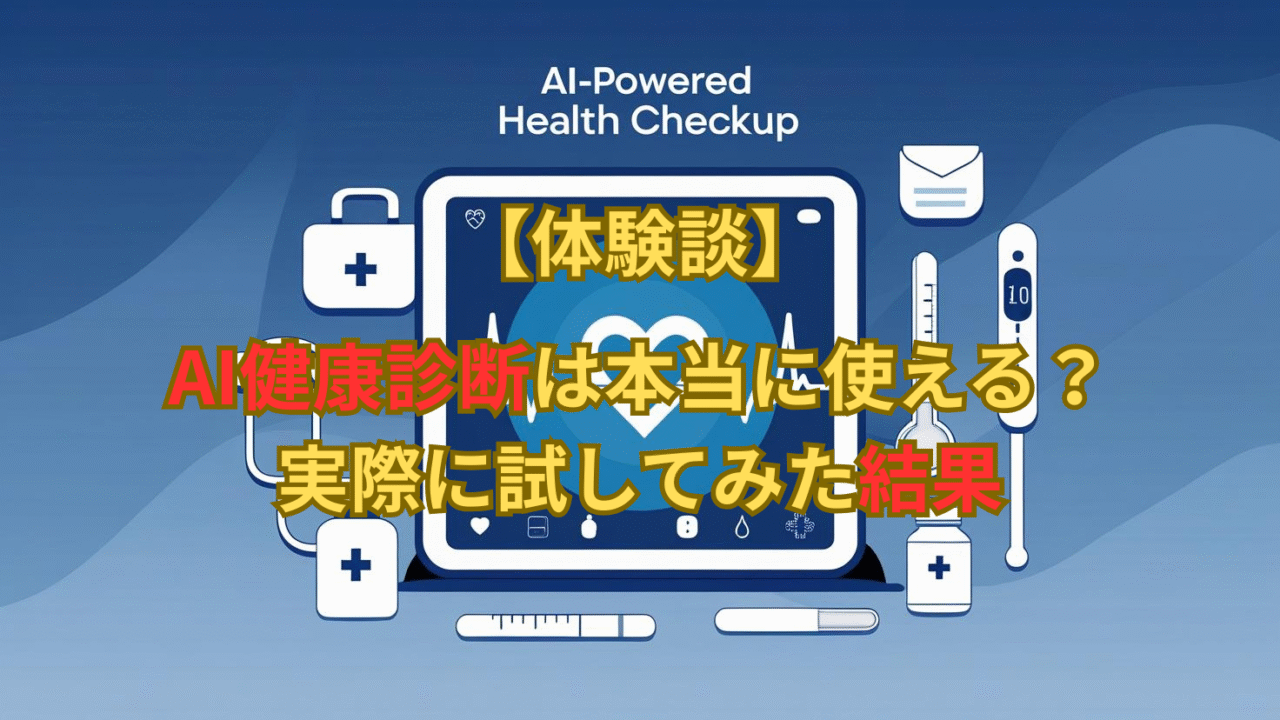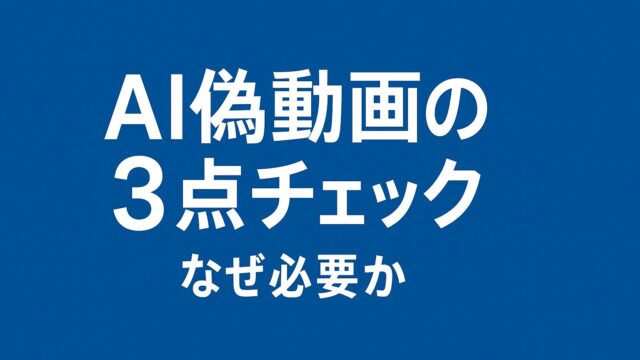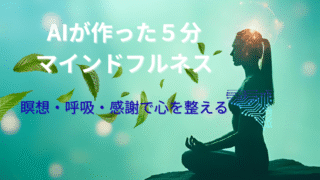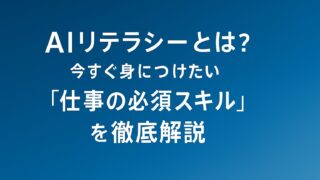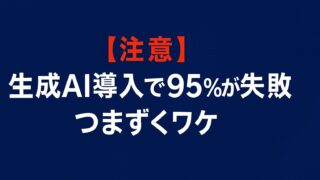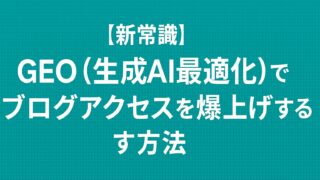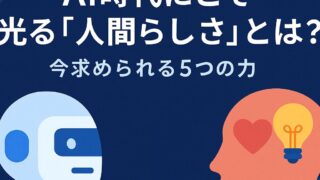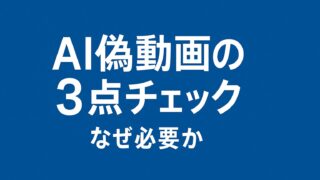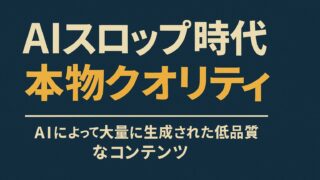導入 – AI健康診断との出会い
最近よく耳にする「AI健康診断 体験談」。
僕も実際にAI健康診断を試してみたのですが、正直、最初は「え、病院行かずに診断って大丈夫なの?」と半信半疑でした。
健康診断といえば、採血やレントゲンなど、病院や検診センターでやるイメージが強いですよね。
それがスマホやパソコンで、しかもAIが診断してくれるなんて、なんだか未来すぎて信じきれませんでした。
でもSNSやニュースで話題になっているのを見て、「忙しくても自宅で診断できるのは便利かも」と思い、ついに試してみることに。
特に僕のように仕事が忙しくて病院に行く時間が取りづらい人にとって、この手軽さは魅力的です。
この記事では、僕が実際にAI健康診断を受けてみた体験談を、
-
どんな流れで使ったか
-
出た結果はどうだったのか
-
精度や使いやすさはどうだったのか
まで、リアルにお伝えします。
AI健康診断に興味はあるけど「本当に使えるの?」と迷っている人は、ぜひ参考にしてください。
AI健康診断体験談|サービスの仕組みと特徴
AI健康診断は、その名の通り「人工知能を使った健康チェックサービス」のことです。
従来の健康診断との違いは、医師が直接診断するのではなく、AIが蓄積された医療データや統計をもとに分析してくれる点。
利用方法は大きく分けて2パターンあります。
-
アプリやWebサイトに症状や生活習慣を入力するタイプ
-
スマホのカメラやウェアラブル端末で測定するタイプ
入力する情報は、身長・体重・年齢・生活習慣(食事、運動、睡眠など)から、血液検査や画像データまで様々。
AIはそれらのデータをもとに、リスクの可能性や生活改善のアドバイスを提示してくれます。
代表的なサービスには、写真2枚で体組成を推定するBodygramや、心拍やストレス状態を解析するWelltoryなどがあります。
もちろん、医師の診断書にはならないので、あくまでセルフチェックや予防のための参考として使うのが前提です。
僕のAI健康診断体験|手順と使用感
今回試したのは、スマホから使えるBodygramというAI健康診断アプリ。
写真を2枚撮るだけで、体型や内臓脂肪量、基礎代謝などを推定してくれます。
手順はめちゃくちゃ簡単。
-
アプリをダウンロード
-
身長・体重・性別などを入力
-
全身の正面・側面を撮影
-
数十秒待つだけで診断結果が表示
診断までの所要時間は3分程度。
使ってみた印象としては「え、こんなに早いの?」というスピード感。
しかもUIがシンプルで、説明を読まなくても直感的に操作できました。
AI健康診断体験でわかった結果と精度の印象
結果画面には、体脂肪率や筋肉量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMIなどがズラっと表示。
さらに「生活改善ポイント」まで教えてくれます。
数値は、以前病院で計った健康診断結果とほぼ近い値。
正直、「思ったより当たってるな…」というのが第一印象です。
ただ、やっぱり血液検査や心電図などの内部データまでは見られないので、精度的には“セルフチェック用”という感じ。
でも、毎月やって変化を追うには十分すぎる内容でした。
AI健康診断のメリット・デメリットと活用法
メリット
-
病院に行かなくても自宅で診断できる
-
短時間で結果がわかる
-
無料または低価格で使えるサービスが多い
-
データを蓄積して経過を追える
デメリット
-
医師の正式な診断ではない
-
血液や画像検査など、内部の詳細まではわからない
-
サービスによって精度に差がある
活用法
-
定期的なセルフチェックで健康意識を高める
-
生活習慣改善のモチベーションに使う
-
病院受診のきっかけづくりにする
健康に関する信頼できる情報は、厚生労働省 e-ヘルスネットでも確認できます。
AI健康診断は「これ一つで完璧!」というより、「健康の見張り役」として使うのがベストだと感じました。
まとめ
AI健康診断は、忙しい現代人にとってかなり便利なサービスです。
短時間で、自宅にいながら健康状態の目安を知ることができるのは大きな魅力。
ただし、あくまで目安であり、体調に異変を感じたら必ず医師の診察を受けるべきです。
僕自身、今回の診断結果をきっかけに運動や食生活を見直そうと思いました。
「最近、健康診断サボってるな…」という人や、「病院に行く時間がない」という人は、一度試してみる価値アリです。
うまく活用すれば、日々の健康管理がぐっと楽になりますよ。
関連記事
- AIが気づいた「あなたの生活習慣の意外な盲点」とは?
- AIで睡眠の質を可視化したら、疲れが取れない理由が見えてきた話
- AIで食事管理が超ラクに!健康と時短を両立する方法
- 健康になりたいのに続かない…そんな人こそAI活用が最強な理由
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。